参加生徒27名 教員3名で4泊5日の台湾研修に出発します。事前学習や事前交流を行い、良い研修になるように取り組んできました。いよいよ出発です。
まず、8時30分に本校大会議室に集合し、結団式を行いました。始めに、佐山校長先生から「サイエンスについての知見を広げると共に多様な価値観を持つ人たちと協働できる力を育んでほしい。何より楽しんできてほしい」との挨拶をしていただきました。また、207HR佐中さんが代表で、「積極的に学ぶ姿勢を持ち、交流や実習に主体的に取り組んできます」との宣言をしてくれました。
結団式の後、バスで関西国際空港まで移動し、無事出国、予定通り桃園国際空港に到着しました。食事も終え、苗栗市のホテルに到着したのは現地時間の21時00分(日本時間22時00分)。長距離の移動で少し疲労がありますが、いよいよ明日は竹南高級中学校との交流、英語での課題研究の発表並びに理科実験があります。準備してきた成果が出せるように頑張りたいと思います。

11月23日(土)と24日(日)に阿南市科学センターにて開催されました。今日は二日目です。昨日は大勢の方が来られて用意していたセットが底を尽きそうになるなど、うれしい悲鳴が上がりました。日曜日ですから今日はもっと多くなりそうです。急遽セットの数を増やすことになり、早めに来館した生徒たちと準備に大わらわでした。
10時より少し早めの開場と共に早速お客さんが来られました。昨日のスタッフと交代しているので上手く説明できるか不安でしたが、しっかりと受け答えしているので大丈夫のようです。将来教員になりたい人やイベントスタッフを経験したい人など応募動機は様々ですが、貴重な体験ができていると思います。当番制で門外での全体受付をこなしながら交代で昼食を取り、来場者に応対しながらも次の準備をするといった作業を繰り返すのは大変です。しかし、途中で根を上げる人もなく最後まで根気強く活動しました。
こうして無事に2日間の日程を終えられました。渡した小ビンのセットが合わせて360個、ブースへの来場者数は約560名です。センター全体での来館者数は約1200名ですから、実にほぼ半数の方に来て頂いたことになります。このことに生徒たちと共に喜び、来年も頑張ろうと再び気合いを入れました。
科学の祭典のブース3「宝石を探そう」にご来場の皆様、誠にありがとうございました。スタッフ一同より御礼申し上げます。

11月23日(土)と24日(日)、今年も阿南市科学センターにて「青少年のための科学の祭典」が開催されました。このイベントは毎年秋に行われており、城南高校科学部も毎年ブースを開設して参加しています。内容は簡単な工作や観察実験、昆虫や化石などの展示、センターの施設を利用した各種体験などです。私たちのブースでは、昨年と同様に「宝石を探そう」を実施しました。
一週間前から準備にかかりました。まずラベルを作り、小袋に小ビンとキャップ、ストラップなどを詰め込んで、来場者に配布するセットを用意します。2日間実施するため300個ほど用意しました。また、ストラップの作り方を書いた説明書など来場者の立場になってわかりやすいように工夫しました。こうして当日を迎えました。
初日は土曜日だったので人出も少なく少し寂しい出だしでした。本校のブースは2階にあるため、先に1階を回った方が2階に来るまで時間がかかります。しかし、毎年出店しているため近年では知名度が高くなり、開場早々に来場がありました。内容としては、溶岩が粉砕されてできた黒い砂に含まれるペリドットを小ビンに採集する作業です。事前に溶岩の話をしたり、ペリドットの由来を説明して砂の中からウグイス色の結晶を探してもらいます。

30分後にはほぼ全体のスペースが埋まりました。小さいブースが多くて一度に大人数が参加できません。そこであえて時間制限なしで採集し放題にしたところ、他との時間調整もかねてここに集まったようです。砂にはペリドットの他に水晶片やクロム鉄鉱を含む砂鉄、軽石、火山ガラスなどが含まれています。来場した子どもたちにこれらを説明しながら、たくさん採って持って帰られるように応援しました。小粒ですからなかなかいっぱいにはなりません。それでも時間と根気が続く限り頑張っていました。こうして10時開場、16時閉場の6時間で150個の小ビンがなくなり、保護者を含めて約230名の方が来られました。明日はもっと忙しくなりそうです。

11月23日(土)13:00~ 「第一回徳島県SSH高等学校課題研究及び科学部研究研修会」が徳島大学理工学部で行われました。「徳島県SSH高等学校課題研究及び科学部研究研修会」は、課題研究を実施するに当たって最も大切である、テーマ決めの実習として、徳島大学理工学部のご助力を得て、本校が主となり実施しております。
県内課題研究の発展のため、県内の高校へ参加を促し、一緒に実施しております。今年度は、県内5校113名の生徒、16名の教員の参加があり、遠方の高校は1校はオンラインで、残りの4校は徳島大学理工学部で対面で実施しました。指導については、徳島大学の先生方8名、TAとして大学院生3名、参加教員16名で指導に当たっていただきました。
内容は、昨年度から改善し、「良い課題研究について」の例を分かりやすく伝えていただきました。さらに「研究倫理について」の講義について、生徒の実態に応じた形に改編し、実施していただきました。「研究倫理について」は、研究ノートを確実に書き、残していくことの重要性などを中心に説明していただきました。
その後、「研究テーマの選び方と研究のすすめ方」について、ブレインストーミングとKJ法によってアイデアをまとめていくという手法を体験的に学びました。研修は3つのSTEPに分かれ、STEP1では、興味があることを自由に上げ(抽象)、STEP2では、その中で、分かっていない解明されていないと思われることを上げ(やや具体に)、STEP3では、どのようにしたら明らかにすることができるか(具体に)各テーマについて班ごとに活発な話し合い、発表が行われました。自分達の興味のあることを研究に発展させるイメージをつかんでもらったと思います。この研修をきっかけとして、各校で課題研究のテーマと研究計画を考えていくことになります。


令和6年11月29日(金)の午後、香川大学教育学部の笠先生をお招きして、応用数理科1年生107HRを対象に,課題研究に関する高大連携授業を行いました。
導入では,理科の授業と探究活動の違いを考え、証拠を示すことの重要性、論理的思考や実験の計画について一緒に考えました。
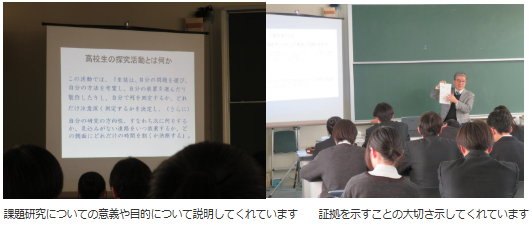
さらに「変数(variable)」を意識することで、探究活動がより楽になるとの説明をしていただきました。そこから、「変数とは何か」と問いかけて、様々な種類の本から変数を見つける活動や様々な図形の中の変数とその値を考え、さらに複数の変数の間における関連性を考える活動を行いました。

その後、「アクリル板と金属板の上では氷の溶ける速度は変わるのか。またそれはなぜか?」について考え、理由を科学の言葉を使い説明することを求めました。そのアシストとして、図で説明してから、言葉で説明する練習をしました。私自身、論述の指導方法について新たな視点を得ることができました。
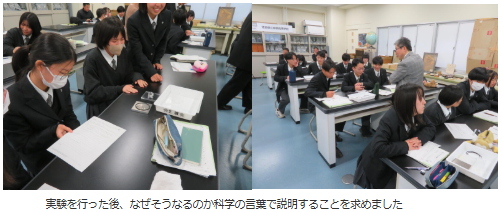
アクティブラーニング型授業であり、課題研究等で養われるゆっくりとした思考(スローシンキング)を求める授業でありました。じっくり考えることでより深い思考を体験し、科学技術人材に必要な思考力を高めて欲しいと思います。