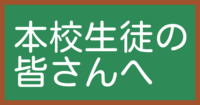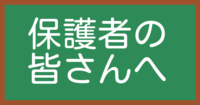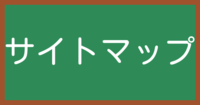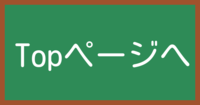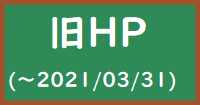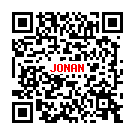スクールポリシー・学校紹介等
令和6年度徳島県公立高等学校入学者選抜について、次のとおり案内します。(11月17日更新)
スクールミッション(本校が目指す学校像)
スクールポリシー(本校教育活動の3つの方針)を策定しました。
下の画像をクリック(タップ)すると、全体がご覧になれます。
学校案内 学校紹介① 学校紹介②
校則の見直しについて ←クリック(タップ)してください。
令和5年度城南高校「公開授業」のご案内
令和5年度城南高校「公開授業」について、次のとおり案内します。
<感染症対策のためのお知らせ及び連絡事項について>
2023/09/27 新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザへの対応について【下記をクリックしてください】
新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザへの対応について.pdf
2022/2/28 新型コロナワクチン接種に関する差別やいじめの防止について
2022/2/16 家庭での感染予防対策に役立つ動画(徳島保健所作成)の案内
1 動画タイトル ・家庭でできる新型コロナウイルス対策〔家族に感染の疑わしい方がいる場合編〕
2動画タイトル ・家庭でできる新型コロナウイルス対策〔基本編〕
新着情報
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
訪問者数(since 2024/04/18)
0
0
0
0
1
3
6
6
0
訪問者数(since 2021/04/01)
0
0
7
3
1
3
3
8
5
訪問者数(since 2004/11/11)
0
1
2
4
2
9
0
3
4
吹奏楽部・合唱部
<資料>
歴史(とき)をこえて
~今日のわたしから明日のあなたへ~
文部科学省
スーパーサイエンスハイスクール指定校
<城南高>携帯・スマートフォンサイト